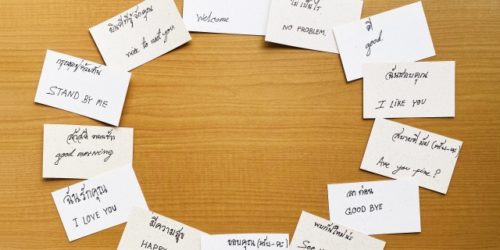反射炉とは?仕組みは?何をするもの?どこにある?
DASH島でTOKIOが作ったり、世界遺産に登録されたりと、何かと話題の反射炉。
そもそも、反射炉とは何か? 何をするためのものなのか?
仕組みや規模、日本で残存する反射炉はどこにあるか?
そのあたりを簡単に解説。
反射炉とは?仕組みは?どこにあるか?
反射炉とは、端的に言うと鉄を溶かすための炉です。
仕組みは、ドーム状の炉内で熱を一点に集め、鉄を溶かす。
Wikipediaによれば
熱を発生させる燃焼室と精錬を行う炉床が別室になっているのが特徴。燃焼室で発生した熱(熱線と燃焼ガス)を天井や壁で反射、側方の炉床に熱を集中させる。炉床で金属(鉄)の精錬を行う。
さらに、
鉄鋼の精錬では転炉など他の方式に取って代わられ使われることはなくなったが、現在でも銅製錬、再生アルミニウムの融解炉として使われている。
とのこと。(Wikipedia 反射炉)
DASH島の反射炉の制作過程でもあったように、大きさの少しずつ異なる支保工を支えにしてレンガを積み上げて、段々細くなるトンネルを作っていました。
火を燃やす部分と、鉄を溶かす部分が別々になっていて、火を燃やし、その熱を天井で反射させて溶かすべき鉄に当てる事で温度を上げるため、炉内はアーチ状、ドーム状になっており、パラボラアンテナのように反射した熱が一点に集まる形状になっています。
鉄を溶かす炉床の先は細くなっており、煙突につながっています。
細くすることで、気流が強くなり、煙突を上る上昇気流と相まって炉口から取り込む空気を多くできるそうです。
DASH島では、煙突の高さを出せなかったので、煙突を2本に分岐させ高さを半分に抑える工夫が施されました。
反射炉、どこにある?場所は?
日本の反射炉は江戸時代後期に海の防衛の必要性から西洋式の大砲が必要となり、従来の日本の技術では製造できなかったため、諸藩が海外の技術書を基に作り始めたものです。
江戸時代末期には、伊豆国、佐賀藩、薩摩藩、水戸藩、萩藩などが反射炉を作り、それらの一部が現存しています。
有名どころでは、世界遺産に登録された韮山反射炉。
静岡県伊豆の国市にある、築造当時の形で現存する反射炉です。
2015年、「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産として世界遺産に登録されています。
同じく、「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産の一つである、山口県萩市の萩反射炉。
こちらは、築造当時の煙突部分のみが遺構として残っています。
そのほか、鹿児島県鹿児島市の仙厳園内に土台のみがあり、佐賀県佐賀市にあった築地反射炉は、跡地が小学校となり、縮小復元と記念碑があります。
まとめ
- 反射炉は熱を反射させ鉄を溶かす
- 江戸時代後期~末期に各藩で作られた
- 韮山反射炉、萩反射炉が現存(いずれも世界遺産)